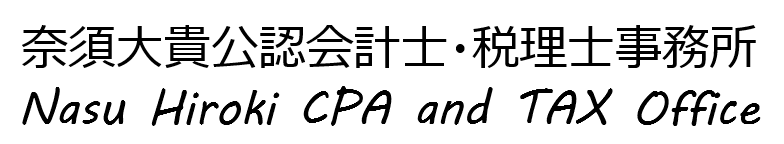皆さん、こんにちは!
福岡市を中心に活動しています公認会計士・税理士の奈須大貴です!
「給付付き税額控除」という言葉を最近よく耳にするようになりました。物価高騰が続くなか、所得に応じた支援を税制で実現し、低所得層のみならず中間層にも恩恵が及ぶ制度として注目されています。
諸外国では、アメリカのEITC(Earned Income Tax Credit)、イギリスのユニバーサル・クレジットなど、同様の仕組みがすでに広く普及していますが、日本でも制度の導入に向けて議論が始まりました。
そこで今回は、「給付付き税額控除」がどのような制度なのか。そのポイントを解説します。
給付付き税額控除の特徴
「給付付き税額控除」の最大の特徴は、税額控除に加えて、控除しきれない分を現金で給付する仕組みにあります。
仮に、「税額控除額が3万円」のケースを例に見てみましょう。
- 「納税額が控除額より多い」Aさんの場合(所得税額 8万円)
→所得税額8万円から3万円が控除され納税額は5万円に減る。 - 「納税額が控除額より少ない」Bさんの場合(所得税額 2万円)
→所得税額2万円から3万円が控除され、控除しきれなかった1万円が現金で給付される。 - 「所得税を納めていない」Cさんの場合
→納めている所得税が0円なので控除できないが、控除しきれなかった3万円が現金で給付される。
このように、「給付付き税額控除」は、納税額が少ない人や非課税世帯にも支援が届くのが大きな特徴です。
これまでの支援制度との違い
これまでの支援制度と比べてみましょう。
2024年6月に実施された「定額減税」は納税者に広く恩恵がある一方で、納税額が少ない低所得者や非課税世帯には恩恵がほぼありませんでした。そのため定額減税の対象外となる世帯に対しては、政府が別途「給付金制度」を設けることとなりました。
また、コロナ禍で行われた「一律給付金」は、全国民に公平・迅速に支援が届く一方で、高所得者にも同額が支給され、支援の効率が悪くなりました。
「給付付き税額控除」は、限られた財源の中で、より必要とする人に重点的に支援を届けることが可能です。
一方でデメリットもあります。「給付付き税額控除」は制度設計が複雑で、給付対象者の特定に行政的なコストと時間がかかる、というものです。
「給付付き税額控除」の制度化へ向けた動き
2025年9月30日から自民党・公明党・立憲民主党の3党が、「給付付き税額控除」の制度導入に向けて協議を開始しました。これまで立憲民主党は、給付付き税額控除を先の参院選の公約の柱として掲げており、与党がその協議に応じたかたちです。
- 誰を対象にするか(支援対象となる所得水準の設定)
- いくらにするか(控除額・給付額の設定)
- どのような手段でおこなうか(税務申告ベース、マイナンバー連携による自動給付 等の給付方法)
- 財源をどう確保するか(所得税・法人税の見直し、歳出の再配分など)
などを論点に、制度設計の詳細が詰められていくことになりそうです。
「給付付き税額控除」は、税制と社会保障を組み合わせた新しい支援制度です。支援対象の範囲次第では多くの労働者にとって関係のあるものとなります。今後の議論の進展に注目しましょう。
奈須大貴公認会計士・税理士事務所のWebサイトでは、最新の税金情報などを積極的に発信しています。よろしければ、当事務所のWebサイトをお気に入りに登録していただき、定期的にご覧になっていただけますと幸いです。
また、当事務所へのご相談などは、以下よりお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。お問い合わせ