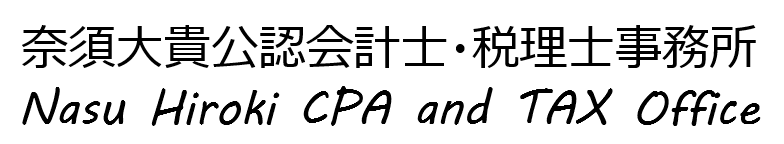【質問】
製造業を営むA社(3月決算法人)では、給与について月末締めの翌月10日払いとなっており、決算期末には、損益計算書の販管費に計上される販売員や事務員の給与及び製造原価として処理される作業員の給与について、3月分の給与を未払費用に計上しています。その場合、「中小企業等における賃上げ促進税制」を適用する場合の雇用者給与等支給額や比較雇用者給与等支給額などの計算では、これらの未払給与はどのように取扱われますか。
【回答】
1 令和6年度の税制改正後の中小企業者等における賃上げ促進税制は、中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額(一定の上乗せ要件に該当する場合には、控除率は最大45パーセントとなります。)の法人税額の特別控除ができることとされています(措法42の12の5③)。
「雇用者給与等支給額」とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいい、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます。)がある場合には、その金額を控除します(措法42の12の5⑤九)。また、「比較雇用者給与等支給額」とは、法人の適用年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額、すなわち、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます(措法42の12の5⑤十一)。
「控除対象雇用者給与等支給増加額」とは、法人の適用事業年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、調整雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を差し引いた金額をいいますが、この計算では、給与等の支給額から雇用安定助成金額も控除して計算します。)を上限とします(措法42の12の5⑤六)。
2 以上のとおり、本税制の対象となる「雇用者給与等支給額」などは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とされていますので、その法人の損金の額に算入されるものに限られ、本来その法人に帰属しないなど、税務上の損金とならない給与等は対象外とされています。
この点、一般管理費などの期間損益である給与等は、未払の給与等であっても適用年度の損金となる給与等の支給額は対象となり、適用年度に支給した給与等であっても前払等の適用年度の損金とならない給与等の支給額は対象とならないものとされています(平成25年度「改正税法のすべて」大蔵財務協会 435頁)。
また、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A(中小企業庁、2024年9月20日更新版)」の「Q28」では、「未払給与、前払給与はどの事業年度の雇用者給与等支給額に含まれるのか。」との問いに対し、「未払給与は、計上時に損金算入されるものなので、その計上時、すなわち損金算入時の事業年度の「雇用者給与等支給額」に含まれます。これに対して前払給与は、計上時には損金算入されないため、その後に損金算入される事業年度の「雇用者給与等支給額」に含まれることとなります。」と回答されています。
したがって、お尋ねのA社の販管費として計上される販売員や事務員の給与については、期末の未払計上額についても、適用年度の損金となるものは、雇用者給与等支給額等とされる「給与等の支給額」に含まれることとなります。
3 一方、このような通常、販管費として処理される給与等に係る一般的な取扱いに対し、資産の取得価額に算入された給与等については、特例的な取扱いが設けられています。
すなわち、本制度を適用する場合の「給与等の支給額」は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になりますが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、その計算を認めることとされています(措通42の12の5-4)。
これは、一般に製造原価を構成する費用である作業員等に係る労務費については、原価計算を通じ、当期中に発生した製造費用のうち製造過程にある仕掛品や未成工事支出金等として棚卸計上される費用を除く製品原価や完成工事原価につき、売上や完成工事高との個別的対応により損金に算入されることとなりますが、このような適用法人における損金算入の時期に合わせて必要な調整計算を行うことはせずに実際に給与等を支給した時期において本制度の適用をすることとしたとしても本制度の趣旨から課税上の弊害は生じないと考えられるためです。
このように、労務費として製造原価に計上される作業員に係る給与については、売上原価等として所得の金額の計算上損金の額に算入される事業年度で「給与等の支給額」に含めて計算する方法が原則的な方法となりますが、仕掛品や製品等の棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、継続適用を条件に、その計算も認められることとなります。
したがって、お尋ねのA社の製造原価を構成する作業員等の給与については、この通達の取扱いにより、実際に損金に算入される売上時ではなく、支給時の「給与等の支給額」として計算することも認められますが、未だ支給されていない期末の棚卸資産に含まれる翌月(翌期)支払いの未払給与は、その事業年度の「給与等の支給額」に含めることはできません。
【関連情報】
《参照法令等》
租税特別措置法42条の12の5
租税特別措置法関係通達42の12の5-4
【掲載日】
令和 7年11月10日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
出典:TKC税務研究所