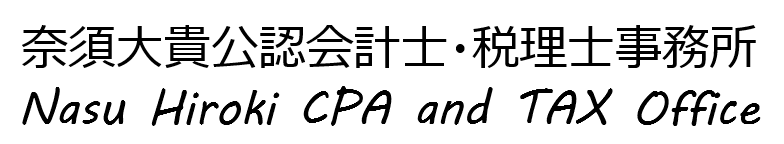皆さん、こんにちは!
公認会計士・税理士の奈須大貴です!
業務委託(外注先)を社員のように扱うと、源泉所得税の未徴収や消費税の仕入税額控除の否認など思わぬ税務リスクが発生します。形式ではなく“実態”で見られる論点と対策をこの記事で解説します。
契約書より“実態”が優先される
最近は、副業・フリーランス活用が広がり、業務委託契約は珍しくありません。
ただし、「契約書に業務委託と書いてある=安全」ではありません。会社が業務の進め方や時間・場所まで管理しているなら、実態としては雇用と判断される可能性があります。ここを誤ると、税務・労務の両面で大きな負担が生じます。
税務リスク:税務署が見る2つの論点
1)源泉所得税の未徴収
実態が給与であれば源泉徴収が必要です。報酬(外注費)扱いで支払い続けていた場合、未徴収分の源泉所得税を会社が遡って負担するリスクがあります(加算税・延滞税を含む)。
2)消費税の仕入税額控除の否認
外注費として処理していても、実態が人件費であれば仕入税額控除の対象外です。支払先から受け取った請求書に消費税が載っていても、会社側で控除できない、という指摘が入り得ます。
労務面で起こり得ること
- 労働局による是正指導(偽装請負・違法派遣の疑い)
指揮命令や勤務時間管理があれば、委託ではなく派遣に近いとして是正を求められることがあります。 - 年金事務所からの社会保険加入の遡及
実態が雇用なら社会保険の適用対象です。過去分の保険料負担が発生する可能性があります。
実態が“業務委託”と評価されるためのチェックリスト
- 契約書に業務範囲・成果物・納期・再委託可否を明記している
- 会社が勤務時間・場所・作業手順を直接管理しない
- 支払いは請求書ベースの報酬(成果基準)で行っている
- 受託者が自らの裁量・自己責任で業務を進められる体制になっている
- 会社の備品・アカウント・名刺などを恒常的に付与しすぎていない(社員同様に見える扱いを避ける)
よくある“グレー運用”が危険な理由
社会保険や税負担を抑える目的で委託に寄せる運用は、短期的にはコスト削減に見えても、後日の追徴で一気に逆転します。人材側の保護の観点でも、実態と契約の乖離はトラブルの火種です。
まとめ:線引きは“紙”ではなく“現場”
- 判断基準は形式ではなく実態
- 税務署は源泉所得税と仕入税額控除を重視
- 労務当局・年金事務所からの是正も想定
- 契約・運用・現場のオペレーションを一体で整えることが防御策
ご相談ください(紹介相談は無料)
「この委託は大丈夫?」「源泉や消費税の処理が不安」
そんな時は、早めの点検が最小コストです。
当事務所では、契約書の観点だけでなく現場運用・会計処理・税務申告まで一気通貫でチェックし、過度なリスクを回避する実務的な改善策をご提案します。
ご希望のある方は、お気軽にご相談ください。お問い合わせ
あなたの夢、会計力で応援します!!!
奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴