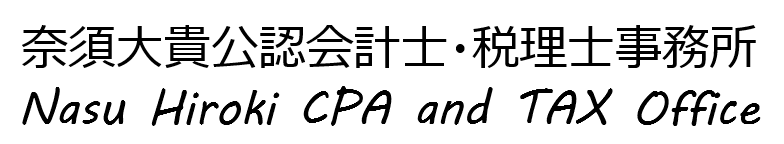令和7年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されました。これにより社員にとっては育児・介護と仕事の両立がよりしやすくなった一方、会社側にとってはさまざまな対応が求められ、その職場づくりが進んでいなかったところでは少し大変だったかもしれません。
「一連の体制整備も終わりホッと一安心」という社長もおられるかもしれません。しかし、本改正のなかには、令和7年10月1日に施行されるものがあることをご存じでしょうか?準備ができていない場合は、早急な対応が必要となりますので、今回はポイントを紹介します。
10月1日から対応が必要な3つの改正ポイント
1.妊娠・出産等の申出時等に社員に働き方の意向を確認する
現行では、社員やその配偶者が妊娠し、その報告を受けたら、会社側は自社の育児休業の制度について説明し、利用するかどうかの意向を確認することとなっています。
令和7年10月1日からは、制度の説明に加えて、以下の4つの内容について社員の意向を確認し、自社の状況に応じて配慮を行うことが義務化されます。
(1)始業および終業の時刻
(2)就業の場所
(3)以下の育児両立支援制度等と、制度を利用できる期間
・育児休業
・子の看護等休暇
・所定外労働の制限の制度
・深夜業の制限の制度
・育児短時間勤務制度(代替措置を含む)等
(4)その他、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
なお、これらの意向確認は、面談や書面の交付等によって行う必要があります。また、この意向確認は子どもが3歳になる前にも必要です。
2.5つの措置から2つ以上を選んで自社に導入する
子どもが3歳から小学校就学前の期間について、社員が柔軟な働き方を選択できるよう、会社は以下の5つの措置から2つ以上を選んで導入することが義務付けられます。
【フルタイムでの働き方を前提とするもの】
(1)始業時刻等の変更
(2)テレワーク等(10日以上/月)
(3)保育施設の設置運営等
(4)新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
【短時間勤務を認めるもの】
(5)短時間勤務制度
なお、もし就業規則がある場合、導入を決めた措置について記載する必要があります。忘れずに改定を行ってください。
3.上記2の措置のうち何を利用するのかを社員に確認する
会社側は、上記2において、仕事と育児の両立を支援する制度を選択・整備したら、対象となる社員の子どもが3歳になるまで(子供が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)の適切な時期に、どのような措置を導入しているのかを伝え、どれを選ぶのかを確認することが義務付けられました。
この意向確認も、面談や書面の交付等によって行う必要があります。
改正育児・介護休業法に関して、本稿では令和7年10月1日から追加で整備しなければならないものについて解説しました。就業規則の改定を含めて、自社の体制を再度確認し、見直すべき点、準備すべき点を早めに確認しておきましょう。